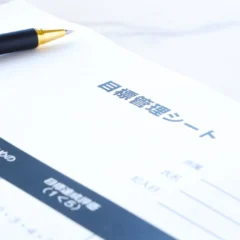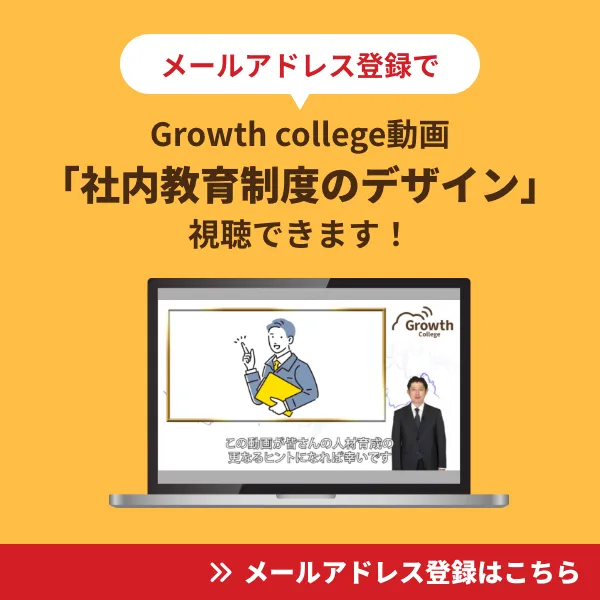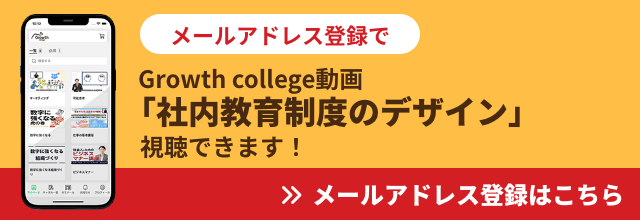会社の成長に欠かせない社員教育とは?実施の目的や手段の種類などについて解説

組織が発展を続けていくには、自社で働く個人の成長を積極的に促進し、企業としての価値や競争力を高めていく必要があります。そのための手段として行われるのが、社員教育です。
そこで今回は、全国に14,000社以上もの会員企業様を抱え、中小企業の社員教育をサポートしてきた日創研が、社員教育とは何か、その目的や方法、進め方等について解説していきます。
また併せて、社員教育を成功させるためのポイントと注意点についても紹介していきますので、自社の社員教育にお悩みの経営者、人事担当者の方は、ぜひ参考としてご確認ください。
目次
社員教育とは
まずは社員教育という言葉の定義について、確認していきましょう。一般的に社員教育とは、企業が自社の社員に教育を施すこと、積極的に学習機会を提供して育てることを言います。
もう少し具体的に言うと、企業組織が自社の経営戦略を実行するにあたり、業務上必要になると考えられるスキルや知識を獲得する機会を社員に提供すること、または教育を通して自社の経営理念などを社員に知ってもらい、組織全体に浸透させることと表現できるでしょう。
なお社員教育は、会社によっては「人材育成」や「人材開発」等と呼ばれることもあります。
社員教育が重要視される理由
「人」は企業組織にとって最も重要な経営資源の一つであるため、人材育成や社員教育の重要性は、昔から経営者の中で強く認識されてきました。しかし近年、さらに社員教育の必要性が強調されるようになってきた理由としては、大きく以下の2点が上げられるでしょう。
企業が発展を続けていくには、組織で働く個人に成長を続けてもらう必要があるから
労働力人口の減少を補うため、一人ひとりの社員の生産性を向上させる必要があるから
少子高齢化が進む中で人材を確保し、企業組織としての競争力を向上させるには、自社の既存スタッフに積極的に学習機会を提供してスキルや生産性、会社へのエンゲージメント(帰属意識)を高めてもらうのが効果的です。
社員教育は、企業が組織として存続し、そこで働く個人と共に成長・発展を続けていくために不可欠な要素なのだと理解しておきましょう。
社員教育を実施する主な目的
企業が社員教育を実施する目的は、その組織が社員教育で達成したいこと・解決したいことにより変わってきます。ただ一般的には、以下のようなことを目的として社員教育が実施されるケースが多いでしょう。
- 社員に日々の業務、また企業にとって必要なスキルや知識を身に着けてもらうこと
- 組織で働く個人の成長を通して、経営目標の達成や業績の向上を実現させること
- 社員の会社への愛着を高めることで、貴重な人材の流出を防ぎ、定着させること
- 社員さん自身に人間として、組織人として自己実現して幸せになってもらうこと
社員教育の手段・種類の具体例

ひと口に社員教育と言っても、そのやり方にはさまざまな種類があります。そのため社員教育は、教育対象となる社員の階層や属性、学習テーマ等を基準に複数の手段を選択し、組み合わせて進めていくのが一般的とされているのです。
そこでここからは、代表的な社員教育の手段5種類の概要について、順に紹介していきます。
【社員教育の手段1】OJT
OJT(On the Job Training)とは、先輩や上司などの指導・監督のもと、実際の業務に挑戦することを通して仕事に必要な技術や知識を身に着けてもらう社員教育のことです。
職場内訓練とも呼ばれるもので、日々の業務の延長として実施できるため現場の負担を軽減しやすいこと、また新入社員や若手社員の教育に適した手段として知られています。
【社員教育の手段2】OFF-JT
OFF-JT(Off the Job Training)とは、業務から離れて時間や場所を確保し、社内または社外で社員教育を行う手段のことです。OJTの職場内訓練に対して、職場外訓練とも呼ばれています。
一般的に社員教育と聞いてイメージするような研修やセミナー、講習会等の集合型の社員研修はOFF-JTに当たり、教育対象によって内容や教え方を柔軟に調整しやすいのが特徴です。
【社員教育の手段3】eラーニング
eラーニングとは、あらかじめWeb上に用意した文章や動画などを視聴してもらって社員教育を進める手法のことです。インターネット環境さえあれば学習機会を提供できるため、社員教育を行う現場担当者と教育対象となる社員双方の時間的、精神的な負担の軽減に役立ちます。
作業の効率化、業務改善、教育マニュアルならGrowth College(グロースカレッジ)
【社員教育の手段4】自己啓発支援
業務に関連する知識やスキル、資格を取得するために企業側がテキストや通信教育の費用等の一部を負担したり、十分な勉強時間を確保できるように勤務時間を調整することも、社員教育の手段の一つです。
このような社員教育法は自己啓発支援、またはSD(Self Development)と呼ばれています。
【社員教育の手段5】コーチング型朝礼
コーチングとは、効果的な質問を返すことによって相手の気付きや成長を促す会話術のこと。そしてコーチング型朝礼とは、コーチング型の質問やコミュニケーション法を取り入れて実施する朝礼のことです。
毎日の朝礼を経営者や経営幹部の話を聞くだけの場ではなく、社員教育の場として有効活用したいという場合は、「13の徳目」を使ったコーチング型朝礼の導入も検討してみましょう。
コーチング型朝礼に利用できる「13の徳目」の内容や特徴とは?
社員教育のメリット・デメリット
企業組織の存続と発展のために非常に重要な社員教育ですが、実施することにはメリットだけでなく、デメリットもあります。そこで以下に、社員教育を行うことによるメリット・デメリットをそれぞれまとめましたので、社員教育の概要と併せて、ひと通り確認してください。
社員教育によって期待できるメリット
- 自社の経営理念や目標を組織全体に広く周知、浸透させる良い機会となる
- 個々の社員のスキルアップ、組織全体の生産性や業務効率の向上につながる
- エンゲージメント向上による人材の定着率向上、離職率低減が見込める
- コンプライアンス研修を実施すれば、組織全体のリスクヘッジにつながる
社員教育を行うことによるデメリット
- 効果が不透明な中、時間的・金銭的なコストをかけて実施しなければならない
- 社員教育により、通常業務に一時的な遅延や効率低下が起こるリスクがある
- 社員教育の実施により、周囲のスタッフに過度な業務負担がかかる場合がある
計画的に社員教育を進めるための基本の5ステップ

社員教育は、場当たり的ではなく明確な目的や目標のもとで計画的に進めていった方が、効果を発揮します。そこでここからは、計画的に社員教育を進めていくための5つの基本ステップについて、大まかに紹介していきます。
自社の社員教育の内容、計画を具体化していく際の参考として、ぜひお役立てください。
【ステップ1】自社の人事理念を確認する
まずは、社員教育の目的や方向性を明らかにするために、自社の人事理念を確認します。
まだ人事理念がはっきりしていない場合は、経営理念と人材戦略から自社が「求める人物像」を導き出し、人事理念を明確にしましょう。
【ステップ2】自社の現状と課題を洗い出す
次に各部署、立場の人にヒアリングを行い、自社が今置かれている状況を把握します。
また現状を踏まえ、経営上・人事上の理由から自社が早急に解決を目指すべき問題や課題は何か、洗い出していきましょう。
【ステップ3】社員教育の目標を設定する
自社にとっての「経営上・人事上の課題」が見えてきたら、そのうち、社員教育で解決可能なものを選び出し、組織全体としてどのようなことを目的・目標として社員教育を進めていくのかを決定します。
その後、全体としての社員教育の目標をベースに各部門や部署、チーム単位の社員教育の目標も設定していきます。なおこの時、部署や部門単位の目標の方向性を組織全体の社員教育の目標と一致させること、併せて目標達成の期日も設定することを忘れないようにしてください。
【ステップ4】スケジュールを具体化する
設定した目標と達成期日から逆算して、いつ頃、どのような内容、手法、頻度で社員教育を実施するのかを一つずつ決めていき、社員教育に関するスケジュールを具体化していきます。
【ステップ5】効果測定の方法を設定する
社員教育は、実行した教育施策の効果を確認し、フォローや振り返りを行って初めて完了するものです。そのため計画的に社員教育を行うには、スケジュールや提供する教育施策等と一緒に、効果測定やフォローアップの方法まで具体的に決めておかなければなりません。
効果測定の方法としては、アンケートや面談、聞き取りの他、テストで学習内容やスキルの定着度を測る等が考えられます。社員教育の目的や教育施策の内容により、適切な効果測定やフォローの方法は変わってきますので、計画段階からしっかり検討しておきましょう。
社員教育を成功させるためのポイントと注意点まとめ
社員教育を計画的かつ効果的に進め、成功させるには、いくつか押さえておくべきポイントや注意点があります。そこで以下に、計画の立案や施策の実行、効果測定、振り返り等の一連の社員教育を行う上で知っておくべきポイントと注意点について、まとめて紹介していきます。
自社の社員教育に注力する際は、以下に挙げたような視点や考え方を忘れてしまわないように注意してください。
- 社員教育を受ける立場である社員さんには、必ずその目的を明示・共有する
- 社員教育の計画や学習内容は、時代や社員の特性の変化に合わせて改善する
- 社員教育に用いる手段の種類、組み合わせについても、定期的に見直す
- 学習機会を提供して満足するのではなく、その後のフォローもきちんと行う
- 社員教育を主導する立場である経営者や経営幹部、管理職が率先して学ぶ
社員教育は「組織」と「働く個人」両方を意識して進めよう

企業はそこで働く人材がいなければ組織として成り立たず、会社としての価値や競争力を保つこともできません。そのため、社員教育は組織としての成長や経営上の目的・目標の達成だけを目指して行うのではなく、社員さんの成長や幸福も意識して進めていく必要があるのです。
社員教育を成功させるには、企業組織だけでなく、共に働き成長を目指すことになる社員さん達の成功や幸福にも重点を置いて、計画・実行していく必要があると覚えておきましょう。
なお日創研では、一人ひとりの社員さんの強みや弱み、能力、課題、思考パターン等への自己理解を促進し、仕事や働き方への考え方をアップデートさせるセミナーとして「SA自己成長コース」を開催しています。
自社の目的達成のためにどのような社員教育を実施すべきかわからない、スキルや知識の獲得よりも先に、仕事への価値観を変えるための学習機会を提供したいとお考えの場合は、日創研の「SA自己成長コース」を社員教育に導入することもご検討の上、お気軽にご相談ください。